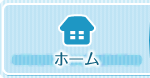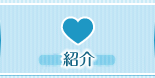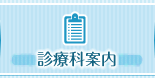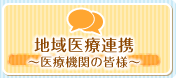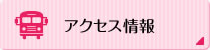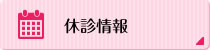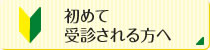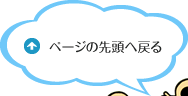- 股関節
- 脊椎
- 骨延長・変形矯正
- 先天性・系統疾患/症候群
- 下肢・足
- 脳性麻痺
- O脚・X脚
- 内反足
- 先天性内反足
- 先天性側彎症
- 乳・幼児高度側彎症
- 脊柱側彎症
- 症候性側弯の治療
- 特発性側彎症
- 軟骨無形成症
- 二分脊椎症
- 骨形成不全症
- 多発性関節拘縮症
- ダウン症
- 大腿骨頭辷り症(大腿骨頭骨端線離開)
- 化膿性股関節炎
- 股関節脱臼
- ペルテス病
- ペルテス病の診断
- ペルテス病の概略
- ペルテス病にたいする保存療法の実際
- ペルテス病の治療概略
- ペルテス病にたいする手術療法
- 先天性股関節脱臼タイプ別治療法
- 開排位持続牽引整復法
- 治療後の股関節の発達
- 乳児期の臼蓋形成不全
- 先天性股関節脱臼の治療
- 先天性股関節脱臼の手術的治療
- 開排位持続牽引整復法の年別症例数
- 先天性股関節脱臼の概略
- 先天性股関節脱臼の予防
- 先天性股関節脱臼の発生頻度
- 先天性股関節脱臼の原因
- ベビースリング
- 抱き方
- オムツの当て方
- バクロフェン髄腔内投与療法
乳児期の臼蓋形成不全
臼蓋形成不全とは、股関節の臼蓋を構成する骨組織(特に腸骨)の発育が不十分で、骨頭を十分に覆うことが出来ない状態を言います。多くの研究者は、臼蓋の腸骨部分の傾きを計測し、乳児で30度以上ある場合を臼蓋形成不全と定義しています。
1.臼蓋形成不全の原因
臼蓋形成不全の原因については長い間論争がありました。「臼蓋不全があるために脱臼が発生したのか?」、それとも「脱臼があるために臼蓋形成不全がおこったのか?」という意見の対立です。現在では多くの研究者が、脱臼があるために臼蓋形成不全がおこったと考えています。なぜかというと、脱臼は臼蓋形成不全を伴うことが多く(全部ではありませんが)、逆に脱臼が整復されると多くの場合臼蓋形成不全が改善するからです。言い換えれば、骨頭と臼蓋との関係が正しければやがて臼蓋は形成されてくる、というのが大多数の専門家の意見です。私達も基本的には同じように考えています。しかし、遺伝的要因の強いごく少数の例に脱臼を伴わない臼蓋形成不全があることを確認していますが、このことについては別の機会にお話致します。
脱臼治療開始が遅れた場合には、臼蓋形成不全が残存するのが普通です。臼蓋は正しい整復位になければ形成されません。骨頭がはずれていた期間が長かったわけですから、臼蓋形成不全が著しいのはやむを得ません。整復がうまくおこなわれたとしても4-5歳までに臼蓋を形成する手術が必要となる場合が多いものです。
2.臼蓋形成不全の三次元的病理
乳児検診において股関節の開排(股関節を曲げかつ開くこと)制限を指摘され、整形外科においてX線撮影の結果、脱臼はしていないけれど臼蓋の発育が不十分である、と診断された場合にどのように対処するかということについて考えてみましょう。先きに述べた理由から、わが国の整形外科学会では、X線写真において、臼蓋の発育が不十分であっても脱臼を認めない場合には、臨床所見(開排制限など)が改善してゆくならば特別の治療をしなくても最終的には臼蓋形成不全は治癒する、という意見が支配的です。私達も基本的にはこの考え方に賛成ですが、超音波断層像やMRIによって詳しく調べてみると、この問題はもっと複雑なことが解ってきました。
1990年代に至り、超音波断層像で脱臼が診断できるようになりました。開排制限などの臨床所見がある赤ちゃんに超音波診断(前方操作法)をおこなうと、「X線画像上、脱臼は無いけれど臼蓋形成不全を認める」という症例では、「ほとんどの場合さまざまな程度の亜脱臼を伴っている」、ということがわかったのです。X線診断で脱臼が判らないことがある、という理由は簡単です。X線診断は三次元のものを投影像によって判断するものですから、股関節伸展位で骨頭が前方に脱臼している場合には診断が困難となる場合があるのです。もちろん、骨頭が前方に転位しているばあいには、同時に外方にも移動しているわけですから通常はX線画像上何らかの異常所見がでてくるのですが、臼蓋が前方に強く回旋している(脱臼していると例外無くこの回旋は健側よりも強い)と投影像では診断不可能なことがある、ということが判りのことと思います。すなわち、開排制限を有し、X線画像上「脱臼は無いけれど臼蓋形成不全を認める」という症例では、前方操作法による超音波診断を行うと「ほとんどの場合様々な程度の亜脱臼を伴っている」ということが明らかになったのです。これらの多くはタイプAIの軽度の亜脱臼なのですが、稀にタイプAIIの亜脱臼である場合があることも判ってきました。タイプAIIの亜脱臼である場合には股関節をどのように動かしても骨頭が正しい位置をとることが出来ないわけですので、骨頭を正しく臼蓋に向ける操作が必要となります。
3.臼蓋形成不全の治療について
1990年から1993年までに本センターを受診したタイプAIで臨床所見の改善した42症例42関節(多くは臼蓋形成不全を伴う)を経過観察をおこないました。初診時に下肢取り扱いの注意、おしめの当て方、抱き方、ミルクの飲ませ方を指導した上で、これらの関節を超音波断層像とX線像によって1年以上追跡したところ、1才までに38関節は正常となり、他の4関節のうち3関節は3才までに正常となり、残りの1関節も4才までに正常となりました。すなわち、臼蓋形成不全があっても、タイプAI脱臼で臨床所見の改善傾向のある例では特別の治療を必要としないことがわかったのです。ただし、臼蓋形成不全の程度が著しい場合には改善するのにあまりにも長期間必要としましたので、1997年からはタイプAIのうち3ヵ月以上で臼蓋形成不全を伴う場合には治療をおこなうことにしています。一方、タイプIIではどうか?といいますと、初診時に下肢取り扱いの注意、おしめの当て方、抱き方、ミルクの飲ませ方を指導した上で、これらの関節を超音波断層像とX線像によって追跡したところ、自然治癒する場合は少ないことがわかりました。
これらの臨床研究の結果から、本センターでは、2000年6月より臼蓋形成不全に対して以下のような方針をとっております。
(1)超音波断層像で骨頭が開排位において整復位(求心位あるいは向心位)にある場合(タイプAI-II)。
タイプAI-IIで生後3ヶ月以上の乳児では入院の上リーメンビューゲルという装具を装着して治療します。入院後、リーメンビューゲルを装着し股関節を開いた状態での牽引をおこないます。股関節が70度まで開くようになったらリーメンビューゲル装着のまま退院します。入院期間は2泊3日です。
タイプAI-IIで生後3ヶ月未満の乳児の場合は、下肢取り扱いの指導のみで経過観察します。
軽度の脱臼であれば、赤ちゃんの育児環境を良好に保つことにより、自然治癒を促すことが可能です。赤ちゃんの下肢取り扱い方法とは、特別に難しいものではなく、その基本は赤ちゃんの下肢の動きを妨げないということです。下肢の動きをなるべく制限しないような薄いおむつ(紙でも布でもかまいません)、おむつカバーを股間に当て、赤ちゃんの下肢の自由な動きを妨げないことが基本です。したがって下肢の動きを制限するようなおしめカバーや衣服は使用しないことが重要です。しばしば見られる誤りは、股の間に厚いおしめを当てることによって下肢を無理やり開かせることです。股関節の開きを強制的に赤ちゃんに押し付けると後に、深刻な股関節変形が生じることがありますので注意してください。赤ちゃんを抱く場合は、抱く人と赤ちゃんとがお互いが向き合うようにするのが大切です。そうすれば赤ちゃんの下肢は自然な形をとり、ある程度自由な運動が可能になります。赤ちゃんを横にして抱くと、下肢の動きが制限されるので横抱きは避けるべきです。よく見られる誤りは、抱くときに、赤ちゃんの股に手を入れることです。このような抱き方をすると一方の下肢の運動が制限されますのでよくありません。赤ちゃんにミルクの飲ませる時も、赤ちゃんがお母さんの膝にまたがるようにします。
上のような対応によっても1-2ヶ月以上にわたって症状の改善が無い場合は3ヶ月以上の乳児と同じように入院の上リーメンビューゲルという装具を装着して治療します。
(2)タイプAIIの治療
まず牽引をおこなって上方に移動している大腿骨頭を引き下げます。その後リ-メンビューゲルというRBを装着して股関節を開いた状態での牽引をおこないます。開排位での牽引で股関節が開くようになったら重垂を少しずつ減らしてリ-メンビューゲル装着のまま退院します。入院期間は2-4週間です。
我が国ではまだx線診断が中心です。この場合、X線写真において、臼蓋の発育が不十分であっても脱臼を認めない場合には、臨床所見(開排制限など)が改善してゆくならば特別の治療をしなくても最終的には臼蓋形成は治癒する、という考え方でたいていの場合は対処できると思います。しかし、今日では注意深い視診・触診と超音波断層像により脱臼の重症度を正確に評価することにより無駄な治療を省くことが可能になっています。
4.先天性股関節脱臼の治療後に残存した臼蓋形成不全
先天性股関節脱臼の治療後に骨頭と臼蓋の適合性は良好となっても臼蓋形成がまだ不十分である場合があります。とくにタイプB、C脱臼の治療後によく見られます。こうした場合にひきつづき治療を行うか否かについては意見が別れています。どうしてこのような混乱があるかというと、治療後に残存した臼蓋形成不全にたいする装具療法の効果についての科学的なデータがないからです。ほんとうは、同じ程度の臼蓋形成不全で同じ年齢同じ性の赤ちゃんを2群に分け、一方には治療を行い、他方には経過観察のみにとどめる、というようにして調べなければならないのですが、様々な理由からまだこれができていません。その為、治療方針は整形外科医師の個々の裁量にまかされているのが現状です。私の印象では昔の先生程装具にこだわっているように思います。
私達の考え方は、「股関節の著しい不安定性があれば短期間(せいぜい3ヵ月、長くても5-6ヵ月)の装具療法を行うことがあるが、安定性があれば経過観察にとどめる」、というものです。不安定性というのは例えば臥位では骨頭は正しい位置にあるが、立位では亜脱臼位置にあるような場合(骨頭の外扁化と呼んでいます)です。ついでですが、どのように股関節を動かしても骨頭が正しい位置に来ない場合は遺残性亜脱臼といって、これは手術的治療を行うなどの治療対象となりますので、ここでは取り上げません。
このような不安定性はタイプB脱臼をリーメンビューゲルで治療した場合には発生するのが普通です。不安定性が軽度であれば通常立位が安定してくるにつれて改善します。私達は、改善傾向が見られない場合や、最初から不安定性が著しい場合にのみ装具療法をおこなっています。ただし後から述べる理由から、装具装着期間は長くても5-6ヵ月を限度にする必要があります。実際には本センターでは開排位持続牽引整復法を始めてから著しい不安定性を呈する症例は皆無となり、1996年以降、乳児期に治療を開始した例に対しては装具装着をしたことがありません。
臼蓋形成不全があっても、立位で股関節が安定している(骨頭は正しい位置をとっている)場合には装具療法は不要と考えています。その第一の理由は、このような臼蓋形成不全にたいして装具療法が有効かどうか判らないからです。装具によって股関節伸展運動は出来なくなるわけですから、外転筋発育が抑制され臼蓋を外に傾ける力が弱くなり、大腿直筋によって骨頭を覆うための臼蓋を前外方に引き下げる力も働かなくなります。内旋・外旋運動が制限されますから臼蓋のY軟骨を押し広げる力も弱くなります。このように理論的には長期の装具装着はいろいろ問題が考えられます。第2の理由は赤ちゃんの知的発達を考えてです。赤ちゃんはすでに脱臼の治療を終え月齢は6-7ヵ月以上になっており、はいはい、坐位、つかまり立ちへと移動機能が急速に発達してゆく年齢になっています。子供はその時期にしか学ぶことが出来ないことを学んでいるはずです。もちろんこの時期治療の為の不自由な生活が5-6ヵ月以内であれば将来の発達にまったく問題ありませんが、1年以上も動きが制限されるとなると話しは別です。装具をつけないと取り返しのつかないことになるならば装具はやむをえません。しかし、今日では著しい臼蓋形成不全が残存しても最終的には確立された安全な手術によって完全な股関節を形成することができるようになっているのです。このような考え方から装具の長期使用は慎重におこなっております。
5.臼蓋形成不全に対する手術療法
4-5歳ころまでに臼蓋形成不全が改善しない場合には手術的治療をおこないます。いろいろな手術方法がありますが、世界中でもっとも普及している方法はソルター手術というものです。この手術は確立した安全なものです。関節そのものを切開しないため、脱臼整復手術とはまったく異なり合併症の危険はきわめて少ない、ということをしっかり認識しておいてください。
ソルター手術(骨盤骨切り術)は、骨盤骨切り術により急峻な臼蓋(骨頭の受け皿)を矯正し、関節の安定を得ることにより将来痛みの出現することの無いような股関節をつくることを目的としています。この手術は、1961年にカナダの整形外科医師、ソルターによって初めて報告された手術です(Journal of Bone and Joint Surgery 161;43B:518-39,1961)。この手術の本質についてソルターは「先天性股関節脱臼がある場合には臼蓋前方の被覆が悪くなっている(言い方を変えれば臼蓋の形成が悪くて骨頭の前方を充分覆うことが出来ていない)。その為、骨盤の骨切りをおこなって、臼蓋を前に倒して(傾けることによって)骨頭を充分に被覆する」、と語っています。この目的に開発されたのがソルター手術です。
この手術の適応は、臼蓋形成不全です。ソルター自身も強調していることですが、亜脱臼を伴っている臼蓋形成不全に対してのソルター手術は禁忌です。専門施設以外では未だにこの原則がまもられていないケースを見かけますので注意が必要です。
- お問い合わせ
- 滋賀県立総合病院
- 電話番号:077-582-5031(代表)